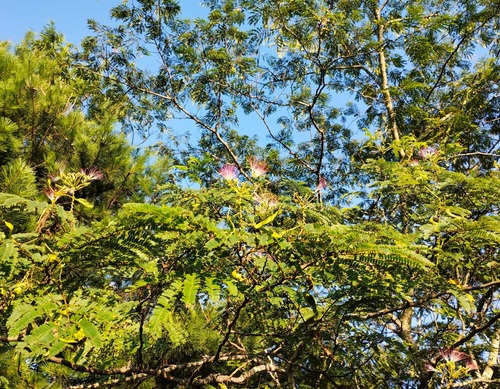なやましき真夏なれども天(あめ)なれば夜空は悲しうつくしく見ゆ 歌人、斎藤茂吉が夏の夜空を歌った一首(歌集『赤光』「夏の夜空」新潮文庫)だ。「過ごしにくい夏の日だが、晴れ渡った夜空は悲しいほどに美しく見える」というような意味だろうか。茂吉の故郷、山形は発生した線状降水帯によって、被害が出た。だが、粘り強い人々は夜空を見上げて、そう遠くない時期にこの歌のような余裕を取り戻すに違いない、と私は信じている。![]()
にほんブログ村 ====
熱帯夜(夜間でも気温が25度以下にならないこと)が明けた早朝、散歩をしていると、森の中からやや小さな声の「カナカナカナ」というセミの鳴き声が聞こえてきた。子どもの頃、このセミのことを「カナカナゼミ」と呼んでいた。ヒグラシだ。漢字では「蜩、茅蜩、秋蜩、日暮、晩蝉」などと書く。晩夏から鳴き出し、夕暮れから明け方まで鳴き続けることもあるそうだ。セミは夏の季語だが、こちらは秋の季語になっている。
あと4日で立秋(7日)だから、季節は確実に秋へと移ろいを始めているのだろう。ヒグラシの鳴き声はそのことを実感させてくれる。とはいえ、言いたくなくとも口から出るのは「暑い」という言葉だ。立秋を過ぎると、「残暑」ということになるが、「猛暑」「酷暑」は当分続くことを覚悟しなければならないのは全国共通だ。
自然の涼しさを求めて山や海に行く人も多い。それも面倒な私は本読んだり、CDを聴いたりして過ごしている。そんな時間、頁をめくった歳時記で「涼風」(夏の季語)が目にとまった。「夏の暑さの中にあってこそ感じられる涼気をいう。朝夕の涼しさ、水辺の涼しさなど、俳句では暑さの中のかすかな涼しさを捉えて夏を表現する」(『合本 俳句歳時記』角川学芸出版)という。例句として芭蕉の「此のあたり目に見ゆるものは皆涼し」が最初に出ている。「この辺の景色は素晴らしく、目に見えるものすべてが涼し気だ」という意味だ。
『笈の小文(おいのこぶみ)』の旅(貞享4年=1687=10月から翌年にかけての上方旅行記)の帰途、岐阜に立ち寄った際、長良川の見える水楼(水辺近く高く造った館)から見た風景を句にしたといわれる。やや平凡という見方もあるが、芭蕉作と聞くと、名句に思えるから不思議だ。「中七の字余り」が目に付くが、さまざまな解釈(「は」がないと小休止する印象になる、「は」によって、全景の素晴らしさが強調されている、など)があるという。芭蕉の遺志を継ぐ江戸中期の俳文集『風俗文選 (ふうぞくもんぜん)には、なぜか中七の「は」はない。
知の巨人(近代の代表的歌人=斎藤茂吉と史上最高の俳諧師=芭蕉)たちの作品を読み、その光景を想像していたら、ひとときながら暑さも忘れた。現在の時刻は午前8時半。窓の外ではクマゼミがかん高い声で鳴き続けている。