今、公私ともに内外の話題になっている大リーグの大谷翔平は、岩手県南部の奥州市水沢区(かつての水沢市)の出身だ。いつものように、地図を見て歴史を調べてみる。ウイキペディアの出身有名人の最初に出てくるのはアテルイ(阿弖流為)で、大谷は最後から2番目にあった。強い指導力で蝦夷の統領として大和朝廷と対立したアテルイ。大リーグで二刀流選手として傑出した存在の大谷。時代を超えて、2人は並び立つ巨人といえる。![]()
にほんブログ村
====
日本歴史大事典(小学館)によると、アテルイは789(延暦8)年に胆沢(岩手県南部)を対象とする朝廷の征夷軍の侵攻に対し、強力な抵抗戦を指導して多大な損害を与えた。しかし、征夷大将軍坂上田村麻呂による胆沢攻略戦の成功に伴い、802年4月にモレ(盤具公母礼)および同族500人とともに降伏した。田村麻呂は助命を主張するが、同年8月モレとともに河内国で処刑された。田村麻呂が創建に関わったという京都の清水寺には、岩手県の有志によって建立されたアテルイとモレの石碑がある。
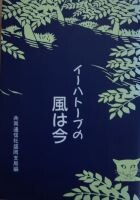 このアテルイ碑の除幕については、手元にある『イーハトーブの風は今』(雲隣舎)という本に掲載されている。この本は共同通信社盛岡支局の記者が1992年4月から95年1月までの2年10カ月に書いた主な記事を季節ごとに分類したもので、私の友人、田口武男氏が支局長当時に出版した。アテルイ碑の記事は京都支局の記者が担当した。前述の文章と少し重なるが、以下はその全文だ。
このアテルイ碑の除幕については、手元にある『イーハトーブの風は今』(雲隣舎)という本に掲載されている。この本は共同通信社盛岡支局の記者が1992年4月から95年1月までの2年10カ月に書いた主な記事を季節ごとに分類したもので、私の友人、田口武男氏が支局長当時に出版した。アテルイ碑の記事は京都支局の記者が担当した。前述の文章と少し重なるが、以下はその全文だ。
《約1200年前、東北地方を平定した征夷大将軍坂上田村麻呂と戦った蝦夷の英雄、アテルイ、モレの顕彰碑が、田村麻呂が建立した京都市東山区の清水寺に完成し6日、除幕式が行われた。碑を建てたのはアテルイの故郷、岩手県水沢市(当時)の出身者でつくる「関西胆江(たんこう)同郷会」。アテルイとモレは朝廷に10年以上にわたって激しく抵抗したが、802年田村麻呂に降伏。田村麻呂は2人の武勇を惜しみ助命を嘆願したが聞き入れられず同年、2人は処刑された。
逆賊とされてきたアテルイらだが近年、郷土を守った英雄として再評価が進んでおり、同郷会が田村麻呂との友情にちなんで清水寺に顕彰碑建立を持ち掛けたところ、寺側も快諾した。碑は岩手県産の御影石で高さ2・5メートル、幅1・7メートル。東北地方の地図を背景に「北天の雄阿弖流為 母礼之碑」と刻まれている》(94年11月6日)
