にほんブログ村
この映画は作家のジャン・ジオノ(1895~1970)が脚本を担当した。しばしば氾濫を起こす南仏プロヴァンスを流れるデュランス川(総延長320キロ)が舞台だ。この川にフランス政府が治水と発電を兼ね巨大なダムを建設する。主人公は、ダム湖の底に沈む村に住む少女オルタンス。ダムの建設によって大地主として巨額の賠償金を得た父が急死したことから、この賠償金をめぐって話が展開していく。映画の主題歌は、ギー・ベアールが作詞、作曲し、ギターの弾き語りで歌った。日本でも中原美佐緒ら多くの歌手がレコードに吹き込んだ「デュランス河の 流れのように」という歌い出し(音羽たかしによる日本語詞)を覚えている人もいるはずだ。
ジオノは、南仏を舞台にした小説を書き続けており、その中に『木を植えた男』( 寺岡 襄 訳・黒井健絵、あすなろ書房)という短編がある。荒れた土地に40年もの長い年月にわたって木を植え続け、緑濃い大地に変えた年老いた羊飼いの話だ。この作品の冒頭に人間観察に対するジオノの考え方が描かれている。
あまねく人びとのことを思いやる
すぐれた人格者の精神は、
長い年月をかけてその行いを見さだめて、
はじめて偉大さのほどが明かされるもの。
名誉も報酬ももとめない
広くて大きな心に支えられたその行いは、
見るもたしかなしるしを地上に刻んで、
はじめてけだかい人格のしるしをも
しかと人びとの眼に刻むもの。
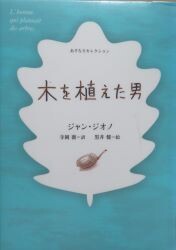 人間の本質は、一目では分からない。長い時間をかけて、こつこつと地道に荒地を緑野に変えた羊飼いの老人こそ、人間としての優れた品性を持っていたのだ。国会で詭弁を弄する政治家とは比べようがないと、私は思う。
人間の本質は、一目では分からない。長い時間をかけて、こつこつと地道に荒地を緑野に変えた羊飼いの老人こそ、人間としての優れた品性を持っていたのだ。国会で詭弁を弄する政治家とは比べようがないと、私は思う。
2017年に66歳で亡くなった葉室麟の時代小説「銀漢の賦」(ぎんかんのふ・文春文庫)は、後の藩家老になる武士と道場仲間の下級武士、さらに2人と偶然知り合う農民の子の友情物語だ。この中で下級武士が、農民たちの先頭に立ち、川に井堰(
水を他へ引いたり流量を調節したりするため、川水をせきとめる所)を造る工事に当たる話が出てくる。彼はすべてを投げ打って川に入って工事に取り組み、周囲から「鬼」といわれながら、堰を完成させる。私はこの武士も「並外れた品性の持ち主」と思うのだ。(この作品はドラマ化されNHKBSで放送され、15日が6回続きの最終回だった)
川と人間の縁は深い。川は災害の源にもなる一方で、多くの恵みも与えてくれる。川をめぐっては、これからも様々なストーリーが紡がれて行くに違いない。《河は今日まであまたの人間の死を包みながら、それを次の世に運んだように、川原の岩に腰かけた男の人生の声も運んでいった》(遠藤周作『深い河』(講談社文庫)
「川」は地表の水が集まって流れる水路のことで、「河」は元々、中国の黄河に対する固有名詞だったが、後に普通名詞になったもので、2つには厳密な区別はないそうだ。
写真 放射冷却で調整池に霧がでた。近くの駅前通りの街路樹、モクレンがようやく開花した。2547「 想い出は帰らず」というが…… 仙台・広瀬川とともに
2546 それぞれの思い出の川「ローレライ」からの連想



